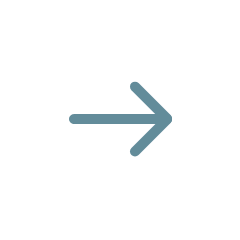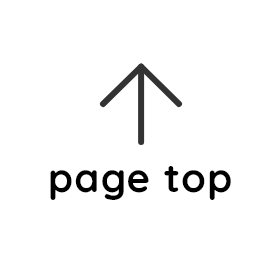65年の歴史に、新たな価値を。時代に寄り添った健診施設を目指して

限界を迎えた施設から、「また来たい」を叶えるために
― ウェルビーイング大阪堂島様の母体である、日本予防医学協会様の歴史と事業についてお聞かせください。
米澤さん:当会は1960年に創立し、日本初の職域における胃がんの集団健診をスタートさせました。以来、健康診断事業を通じて日本の健康を支えています。また、施設健診に加えてお客様のもとへ出向いて健診を行う巡回健診も全国規模で展開。特に胃のレントゲン車は当会が全国で初めて開発・導入した歴史があり、パイオニアとして自負しております。
皿海さん:施設健診と巡回健診の2大柱により、長年蓄積してきたデータやノウハウが当会の強みです。健康状態は常に変化するものですから、個々人のデータを継続的に追い、前回の検査結果からの変化をフィードバックすることが大切です。そうした働きかけにより、受診者の方に健康診断の重要性を感じていただけるよう努めています。
また、職域健診においては、企業ごとの業務内容や環境の違いを踏まえたデータ活用も行っています。例えば、工場勤務の方とオフィスワークの方では健康上の注意点は異なりますから、働く環境に応じたデータ活用とアドバイスをしています。
幸田さん:施設健診と巡回健診に加えて、ネットワーク健診という選択肢もご用意しています。現在、全国約2000の医療機関と提携しており、巡回健診の日程が合わない方や直営の健診施設から遠方にお住まいの方でも、提携医療機関で受診していただける健診スタイルです。結果データは当会がこれまでと同じ形式に加工してお戻しできます。これにより、小規模な営業所や支店で施設健診や巡回健診が難しい場合でも未受診者の発生を防げるだけでなく、全国のデータ一元化が可能です。

日本予防医学協会の歴史を語る、米澤さん
― 全国に4拠点の健診施設がある中で、ウェルビーイング大阪堂島様ならではの特色をお聞かせください。
幸田さん:大阪の受診者は特に時間を大切にされ、予約時間通りの進行を期待されるためスピードが求められます。ただ、中小企業にお勤めの方が多い大阪では、大企業中心の東京の施設とは違った温かさがあります。ざっくばらんにお話しくださる方が多いため距離が近く、アットホームな関係性を築けているのが特徴ですね。
― 長年の拠点だった南森町からの移転を決断された理由を教えてください。
幸田さん:一番の理由は、施設が手狭でキャパシティを大きく超えていたことです。待合スペースのイスは受診者で大変混雑し、隙間なく座っていただかないと足りないほどの状態でした。また、近年はバリウムではなく初めから胃カメラを希望される方が増加したことで、検査の多様化に対応するには設備的にも厳しくなっていました。
皿海さん:60年近い建物なので老朽化が進み、新しいシステムを導入したくても床や天井の構造上不可能な状況だったんです。受診者の増加に伴い血圧計などの機器も増え、本来あった休憩スペースや癒しの空間は徐々に失われていって。最終的には「効率的に早く受診してもらうだけ」の殺風景な空間でした。

大阪ならではの特徴を語る、幸田さん
― 癒やしや快適性よりも「健診をスピーディーに受けてもらう」ことが優先されていたのですね。
皿海さん:そんな中でも、受診者からは「広い場所に移らないの?」「あまり遠い場所に移らないでね」など温かいお声をいただいて。狭い空間でも健診のために足を運んでくださることには感謝しかありませんでした。だからこそ、なんとかその期待に応えたいという気持ちが強かったです。
― 大阪堂島への移転にあたり、特に重視した点をお聞かせください。
米澤さん:広さが約2倍になったので、大阪では珍しい男女別の健診レーンを導入しました。「知らない男性と隣同士で座るのは少し気まずい」という女性の声もあり、効率はもちろん重視しつつも快適性と安心感を優先してチャレンジした形です。
皿海さん:そのため、落ち着ける空間づくりは非常に重視しました。以前の施設よりも天井が高く広々とした環境で、ゆったり受診できる。男女の色分けはあからさまな色で分けるのではなく、木目を基調にしたジェンダーレスカラーで柔らかさと落ち着きを表現したいと考えました。今回の移転にあたって全国の健診施設を視察して、「デザイン性と快適性を追求した空間じゃないと、これからは選ばれない」と強く感じたのも大きな要因です。

大阪堂島への期待を語る、皿海さん
限られた時間の中で実現した、妥協なき空間づくり
― 移転にあたり、どのような課題がありましたか?
米澤さん:最大の課題は、タイトなスケジュールです。2023年の8月に物件を見つけ、実質的な着工は翌年の5月。2025年1月のオープンまで、約半年しかありません。しかも南森町では12月25日まで営業を続けるというスケジュールであり、「こんな短期間で間に合うのか?」「大阪・関西万博による建設資材や人員の影響は?」という不安は拭えませんでした。
皿海さん:加えて、男女別レーンという新しい試み、限られたスペースでの収納確保、医療機器の荷重に耐える床補強、消防法などの法的規制。これらをクリアしながら「落ち着ける空間」という理想を実現する必要がありました。
― 厳しい状況の中、オリバーを移転のパートナーに選んでいただいた理由を教えてください。
皿海さん:複数社に提案をお願いしましたが、厳しい工期に難色を示す会社が多い中、オリバーさんは「やってみます」と前向きに引き受けてくださったからです。スケジュールありきで妥協するのではなく、まずは「できる方法を探しましょう」というスタンスが印象的でした。私たちの理想に寄り添いながらベストなバランスを一緒に考えてくださる姿勢は、心強かったですね。
幸田さん:オリバーさんのプレゼンテーションも、私にとっては斬新でした。医療施設のカタログから選ぶような画一的なものではなく、こちらの想いを汲み取ってコンセプトを提示してくれて。「こんな風にできるんだ!」と、素直に心が動いたのを覚えています。予算などの現実的な問題もある中、「オリバーさんとなら一緒にやっていけそうだ」と感じました。

受付は、心が安らぐカラーと照明を採用。「自然の変化に寄り添う」をコンセプトに、種類の違う家具でリズムを
― 設計や施工の過程で印象的だったことはありますか?
皿海さん:壁やドアの位置を決める工程ですね。レントゲン装置の重量に耐える床補強をすると段差ができ、スロープが必要になる。すると当初予定していた場所に壁やドアが設置できない。消防法で定められた1.4mの通路幅も確保しなければならない。このような制約により、図面上で検討すると狭くて窮屈な配置に見えて、不安になったこともありました。まさに「2歩進んで3歩戻る」ような状況です。
でも、オリバーさんは数センチ単位で壁の位置を綿密に調整し、細部まで検討を重ねてくださって。完成後、想像以上に広がりがある空間に驚きました。

レントゲン室は閉塞感を緩和するため、ジェンダーレスカラーの壁紙や医療家具を採用
― 限られたスペースを活用するために試行錯誤の繰り返しだったんですね。
皿海さん:そうですね。収納に関しても造作家具で対応していただきました。というのも、医療施設は消耗品が多く、収納スペースは必要不可欠です。しかし、受診者のスペースを優先すると、倉庫を作る余裕はありません。そこでベンチの下を収納スペースにしたり、更衣室のロッカー上部に収納を設けたりと、家具の中に機能を持たせる工夫で解決していただきました。

非常時はすぐに対応できるよう、防災グッズなどは受診者用のソファに
幸田さん:今まで医療用カタログから選ぶのが当たり前と思っていましたが、インテリアの素材・色味・種類など、多角的な提案をもらえてとても新鮮でした。ちなみに、ユニフォームを決める際も相談したんですよ。候補のユニフォームから「どのユニフォームなら内装と違和感ないですか?」と。空間全体の調和を一緒に考えて進めていただき、助かりました。

女性レーンは明るく開放的な空間。奥行きのある造作ソファでは、ゆったりと心地よく過ごしている方が多い

男性レーンはグリーンをあしらい、ビジネス街らしい洗練された空間
受診者に愛され、行きたくなる健診施設へ。空間デザインがもたらした効果
― 移転から4か月が経過して、実際にどのような変化や効果がありましたか?
米澤さん:受診者からは、「内装が落ち着いていて心地よかった」「来年もまた来たい」「健診の動線が一直線なので分かりやすい」といった声を多数いただいています。
皿海さん:予約状況にも変化がみられます。受診者数は昨年4月に比べて約3割増え、好スタートを実感しています。以前は午前枠のみの運営でしたが、この空間を多くの方に利用していただきたい思いから移転を機に午後枠を設けたんです。簡易検査の方は午後をご案内することで混雑も緩和され、受診者層の分散につながりました。また、胃カメラの設置台数を1台から3台へ拡充し、胸部CTも導入。これによりご予約も増加しています。
― 空間を一新したことで、新たな発見はありましたか?
幸田さん:女性受診者の過ごし方に変化が見られたのは、大きな発見でした。以前は「早く帰りたい」という雰囲気でしたが、男女別レーンにしたことでゆったりと過ごされるようになりました。男性と同時刻にスタートしても、健診を終えて戻ってくるのは女性の方が遅めなんです。半日の休暇を活かしてリラックスされている姿を見ると、男女別レーンの意義を改めて感じます。
また、この環境は、検査結果にもよい影響を与える可能性があると思います。緊張で血圧が上がりやすい方も、落ち着いた空間ならより正確な測定が期待できるかもしれませんね。

採血時のチェアも、受診者の緊張を和らげるチェアを採用

人間ドック受診者専用ラウンジ。ゆったりくつろいだり仕事をしたり、思い思いに過ごせる
― 今後の展望をお聞かせください。
幸田さん:受診者の方々に愛され、「行きたくなる施設」を目指し続けます。健康診断は義務的なイメージが強いですが、この空間とホスピタリティで「また来年も」と思っていただける施設にしていきたい。それこそが、予防医療の意識づけにもつながると考えています。
皿海さん:移転に伴い、2階に人間ドック受診者専用のラウンジを設けました。受付時にお渡しするコインでドリンクを楽しみながら、医師の面談までの時間を自由にお過ごしいただけます。こうした付加価値も活かして、より多くの方に充実した健診を提供していきたいです。
米澤さん:オープンできて安堵していますが、現状に満足せず、今後も受診者の方々の声を真摯に受け止めて継続的な改善とサービス向上に努めていきます。

(左から)健康管理部 特命課長 米澤 敦史様、健康管理部 課長 幸田 靖子様、健康管理部 部長 皿海 利枝様
※2025年7月時点の内容です。